受診案内
キリストの愛と確かな医療をもって心と体のいやしをめざします。
下肢閉塞性動脈硬化
足の病気が命に関わることも…
下肢閉塞性動脈硬化症とは、足に血液を運ぶ血管がつまり、血液不足に陥った部分が痛んだり,冷えたり、時には壊疽から下肢切断にいたることもある疾患です。初期の症状は歩行時にふくらはぎが重く痛んできて、数分立ち止まって休むとまた歩けるという症状(間欠性跛行)です。この段階で早く発見して治療することが重要で、単なる筋肉痛として見過ごされている例も多く見られます。
この疾患が怖いのは、急に足先が黒くなり(壊疽)、細菌感染がおこってその傷が治らず、やむを得ず下肢切断にいたることです(重症虚血肢)。血行が悪いために免疫物質が届かずに菌の繁殖を抑えられないためです。さらに、下肢の血管がつまる人は、全身の動脈にも同様の閉塞が生じやすく、心筋梗塞や脳卒中が生じやすい事です。
実際、下肢の閉塞症状を伴う患者さんを調べたところ5年後に15%が亡くなっていたという報告もあります。この予後は大腸癌よりも悪いとされています。 人間にとって「歩ける」ということは意外ととても重要で、下肢が痛んで歩行できなくなると糖尿病やコレステロールの悪化、血管を若々しく保っている内皮細胞の劣化、血栓が生じやすくなるなど、様々な因子がからんで心筋梗塞や脳卒中が増加します。
欧米では下肢と生命の関係を「Legs for Life」とよばれ、伝統的に足病医という専門医も確立されています。
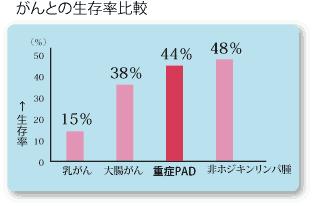
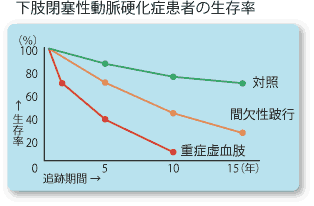
( Am Call Cardiol 2006 )
下肢動脈閉塞の症状
| 初期 | 間欠性跛行 (かんけつせいはこう) |
|
|---|---|---|
| 重症 | 重症虚血肢 (じゅうしょうきょけつし) |
|
どんな人がなりやすいのか
- 45歳以上の男性(閉経後の女性も意外と多い)
- 糖尿病
- LDLコレステロール140以上
- 喫煙
- 肥満
- 高血圧
治療方針
危険因子の改善
- 禁煙
- LDLコレステロール < 100mg/dl
- 糖尿病の改善 HbA1c < 7.0%
- 血圧 < 140/90mmHg
- 糖尿病/腎疾患がある場合 130/80mmHg
薬物療法 抗血小板療法
- アンプラーグ
- アスピリン
- エクバール
- ドルナー
- プレタール
- プロサイリン (50音順)
血行再建術
- カテーテルによる血管内治療
- 外科的バイパス手術

 神戸市二次救急指定病院
神戸市二次救急指定病院






